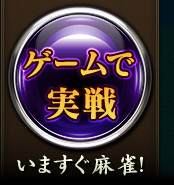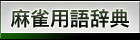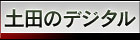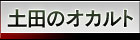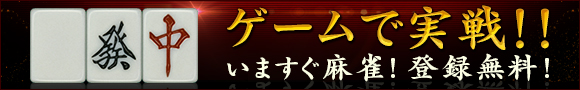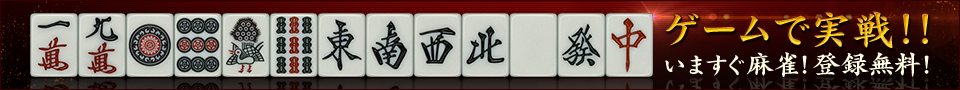手牌は手広く構えたいですが、場面が煮詰まってくると、いつ立直がかかってくるか分かりませんので、押し返す力が手牌には必要です。安全牌が1枚あれば、気持ち的にも押し返しやすくなりますし、まず立直、一発をしのげます。2巡目以降は手牌の形が良ければ攻めますが、安全牌を切って立直といければ一番良いです。中盤の8、9巡目以降の安全牌の抱え方は、一つのテクニックです。早くに安全牌を抱え過ぎるのは、弱気ですし、手狭になります。安全牌を1枚残すということは12枚で戦うということですので、それなりの勝算がなくては残せません。
手牌にドラはなく、![]() は安全牌とします。1・2・3の三色模様の手牌です。
は安全牌とします。1・2・3の三色模様の手牌です。![]() を切れば、
を切れば、![]() か
か![]() が3枚になるか、
が3枚になるか、![]() をもう1枚使える分、若干の受けの広さがあります。しかし、ここは安全牌を1枚残して、安定感のある
をもう1枚使える分、若干の受けの広さがあります。しかし、ここは安全牌を1枚残して、安定感のある![]()
![]() 待ちと
待ちと![]()
![]() 待ちにしたいです。聴牌する枚数は少し減りますが、後々、3枚ある
待ちにしたいです。聴牌する枚数は少し減りますが、後々、3枚ある![]() が相手に当たりかねません。
が相手に当たりかねません。
例えば、次に![]() が入り、三色が確定し、
が入り、三色が確定し、![]() でロンと言われたら、後味が悪いです。これは一つのチャンス手ですから、
でロンと言われたら、後味が悪いです。これは一つのチャンス手ですから、![]() を残して
を残して![]() を1枚切るデジタル的な打ち方が良いです。攻守のバランスを取るには、中盤に入ったら、安全牌を残してもいい手牌かどうかを確認しましょう。
を1枚切るデジタル的な打ち方が良いです。攻守のバランスを取るには、中盤に入ったら、安全牌を残してもいい手牌かどうかを確認しましょう。
ドラは![]() です。平和形のドラ赤の一向聴です。安全牌の
です。平和形のドラ赤の一向聴です。安全牌の![]() をこのまま切り、
をこのまま切り、![]() と
と![]() の暗刻の可能性を残したいところですが、中盤で手を広げ過ぎてしまうと、ぶつかり合ったときにロンされてしまいます。
の暗刻の可能性を残したいところですが、中盤で手を広げ過ぎてしまうと、ぶつかり合ったときにロンされてしまいます。![]() を1枚切っても、
を1枚切っても、![]()
![]()
![]() 待ちの好形です。
待ちの好形です。![]() や
や![]() が3枚になる可能性を追いかけるより、安全度も少し考えましょう。この打ち方が、勝率を高めていく形になります。
が3枚になる可能性を追いかけるより、安全度も少し考えましょう。この打ち方が、勝率を高めていく形になります。
タンヤオ、平和、三色形の一向聴です。![]() や
や![]() といった牌は暗刻になりづらく、また、相手に非常に必要とされやすい牌ですので危険です。
といった牌は暗刻になりづらく、また、相手に非常に必要とされやすい牌ですので危険です。
![]() を切った形です。6・7・8のタンヤオ、平和、三色の一向聴で構えておいたほうが安心感があり、押し返す力も手牌に加わってきます。
を切った形です。6・7・8のタンヤオ、平和、三色の一向聴で構えておいたほうが安心感があり、押し返す力も手牌に加わってきます。
![]() を切った形です。相手からリーチがかかり、
を切った形です。相手からリーチがかかり、![]() で当たると悔やまれます。私的なデジタルでは、中盤でこれだけ手が整っているのであればチャンスです。押し返す意味を込めて、
で当たると悔やまれます。私的なデジタルでは、中盤でこれだけ手が整っているのであればチャンスです。押し返す意味を込めて、![]() の安全牌を残して、
の安全牌を残して、![]() を打ちましょう。これが安全牌残しの典型的な手牌です。
を打ちましょう。これが安全牌残しの典型的な手牌です。