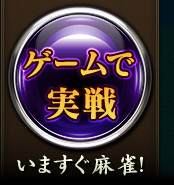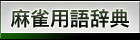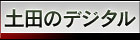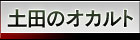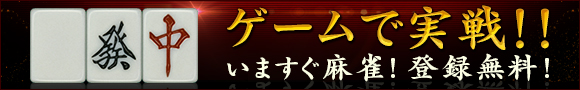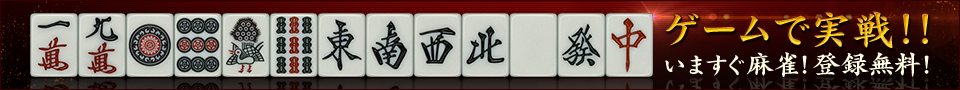土田のデジタル
ゲーム全体の概略(土田のデジタル)
- 1.中盤までは1人麻雀 (約3分50秒)
- 2.打点より形を優先する (約2分30秒)
- 3.ツキの推測はしない (約1分)
- 4.相手に注文をつけない (約2分10秒)
- 5.テンパイ効率より和了効率重視 (約3分20秒)
シュンツの作り方(序盤編)(土田のデジタル)
- 6.孤立牌の選定 (約3分40秒)
- 7.中ぶくれ形の優劣 (約4分20秒)
- 8.4連形の優劣 (約4分20秒)
- 9.ペンチャン形の外し方 (約4分40秒)
- 10.24・68形の壊し方 (約4分30秒)
シュンツの作り方(中盤編)(土田のデジタル)
トイツの作り方(土田のデジタル)
- 15.序盤の河を利用する (約5分50秒)
- 16.壁の外側を温存する (約3分40秒)
- 17.ペンチャンの活かし方 (約6分30秒)
- 18.1枚切れ、生牌字牌の扱い (約3分)
- 19.シュンツとの天秤について (約4分20秒)
- 20.イーペーコー形の活用 (約4分50秒)
- 21.スジ対子論のデジタル的背景 (約2分10秒)
- 22.後からツモってきた牌の価値 (約5分)
序盤の思考(土田のデジタル)
- 23.不要牌の切り順 (約6分30秒)
- 24.数牌の整理法 (約4分20秒)
- 25.ペンチャンの見切り時 (約5分50秒)
- 26.シャンテン戻し (約5分20秒)
- 27.雀頭の作り方 (約8分20秒)
中盤の思考(土田のデジタル)
- 28.手役の見切り (約5分20秒)
- 29.カンチャンと孤立牌の優劣 (約5分10秒)
- 30.雀頭固定打法 (約5分40秒)
- 31.ドラの見切り (約6分20秒)
- 32.安全牌残しの形 (約6分10秒)
終盤の思考(土田のデジタル)
- 33.押し引きの計算 (約3分30秒)
- 34.共通安全牌の貯め方 (約6分50秒)
- 35.形式テンパイとは? (約4分)
- 36.ノーテン罰符の貰い方 (約5分30秒)
- 37.ハイテイずらしの意義 (約2分40秒)
- 38.下家への対応 (約4分10秒)
字牌の扱い方(土田のデジタル)
- 39.絞らずに殺すという考え方 (約4分30秒)
- 40.数牌より先に整理する是非 (約5分30秒)
- 41.鳴ける前提での手順を踏む (約9分10秒)
- 42.トイツ・コーツ手での活用 (約7分)
- 43.三元牌の切り順 (約4分40秒)
- 44.風牌の切り順 (約3分30秒)
- 45.生牌と1枚切れの切り順 (約3分30秒)
- 46.北家の切り順 (約3分40秒)
- 47.安全牌化した字牌の扱い (約6分50秒)
リーチのかけ方(土田のデジタル)
- 48.6巡目までのリーチ (約5分20秒)
- 49.7~12巡目までのリーチ (約2分40秒)
- 50.13巡目以降のリーチ (約4分20秒)
- 51.先制リーチの狙い (約3分10秒)
- 52.追いかけリーチの狙い (約4分)
- 53.爆発リーチのタイミング (約7分30秒)
- 54.手止めリーチの有効性 (約6分50秒)
- 55.究極の出アガリ狙いリーチとは? (約6分40秒)
ダマ聴(ダマテン)に構える手とは?(土田のデジタル)
- 56.6巡目までのケース (約9分)
- 57.7~12巡目までのケース (約6分30秒)
- 58.13巡目以降のケース (約4分20秒)
- 59.速攻 (約3分10秒)
- 60.連荘阻止 (約3分40秒)
- 61.打点系ダマ聴(ダマテン) (約3分50秒)
- 62.マーク者の現物待ち (約3分20秒)
仕掛けの基本(土田のデジタル)
- 63.初動のかけ方 (約6分40秒)
- 64.リャンメン決め打ち打法 (約6分20秒)
- 65.カンチャン決め打ち打法 (約5分)
- 66.対応されない効用 (約5分10秒)
- 67.スピードに乗ったアガリ効率 (約4分50秒)
- 68.孤立牌のレシピ (約5分10秒)
リーチへの対応(土田のデジタル)
- 69.自身がリャンシャンテン時 (約2分40秒)
- 70.自身がイーシャンテン時 (約4分30秒)
- 71.自身がテンパイ時 (約3分30秒)
- 72.自身が手バラ時 (約4分20秒)
- 73.早すぎるリーチへの対応 (約4分50秒)
- 74.0本場親リーチへの対応 (約4分40秒)
- 75.ベタオリ法 (約5分10秒)
- 76.ローリング法 (約5分50秒)
ラス前の思考(土田のデジタル)
オーラスの思考(土田のデジタル)
- 80.点差による戦略 (約4分20秒)
- 81.親番の心得 (約6分30秒)
- 82.トップ目の心得 (約4分30秒)
- 83.ラス逃れ最優先 (約3分37秒)
- 84.役牌の出が甘くなる1局 (約5分50秒)
七対子と対々和狙いの識別(土田のデジタル)
ドラの取捨について(土田のデジタル)
- 90.牌理優先が基本 (約3分50秒)
- 91.打点で利用するケース (約3分50秒)
- 92.もしかしたら…はタブー (約3分40秒)
- 93.ドラ表示牌受けの取捨 (約4分40秒)
- 94.雀頭固定の是非 (約3分30秒)
赤ドラ入り麻雀について(土田のデジタル)
- 95.4・6が主役になる (約3分)
- 96.2・8トイツの重み (約5分)
- 97.ベースの役はタンヤオとリーチ (約5分23秒)
- 98.チャンタや三色は偶然役 (約3分50秒)
- 99.赤入りカンチャンの扱い方 (約3分)
- 100.赤ドラと通常ドラの優劣 (約4分10秒)
- 101.持ち点で考えず、あくまで牌理優先 (約4分)
- 102.赤ドラ切りの効用 (約3分30秒)
レーティング2000を達成するためには(土田のデジタル)
- 103.レーティングとは? (約2分30秒)
- 104.高レーティング者の麻雀を観る (約4分10秒)
- 105.高レーティング者のデータを分析する (約4分40秒)
- 106.牌譜再生機能とは?その活用法 (約4分10秒)
- 107.対局母集団の選定 (約4分10秒)
- 108.自分の方程式を作る (約4分20秒)
受けを強くするために(土田のデジタル)
- 109.巡目とシャンテン数 (約5分10秒)
- 110.シャンテン数とターツの形 (約6分40秒)
- 111.9巡目で決断する (約4分30秒)
- 112.マーク者の安全牌確保 (約4分20秒)
- 113.共通安全牌の確保 (約3分40秒)
- 114.下家のチーへの対応 (約4分20秒)
- 115.ポン仕掛け後の対応 (約4分30秒)
ノーテン罰符の貰いかた(土田のデジタル)
- 116.12巡目を起点にする (約4分50秒)
- 117.トイツ落としを利用する (約4分20秒)
- 118.ターツ落としを利用する (約2分50秒)
- 119.形式テンパイをフル活用 (約3分40秒)
- 120.アガリ牌を喰う (約3分)
- 121.15巡目からは下家をケア (約4分40秒)
- 122.ポンしてテンパイ率アップ (約3分30秒)
カンチャンの評価(土田のデジタル)
カンチャンの外し方(土田のデジタル)
リャンカンの外し方(土田のデジタル)
タンヤオの作り方(土田のデジタル)
- 134.軸になる牌 (約3分)
- 135.Aリャンメンとは (約2分30秒)
- 136.カンチャン複合形を大切に (約6分)
- 137.雀頭にふさわしい牌 (約3分40秒)
- 138.中ぶくれ形を生かす (約2分50秒)
- 139.四連形を生かす (約2分40秒)
- 140.孤立赤牌の生かし方 (約2分40秒)
- 141.喰いタンヤオの使い方 (約3分50秒)
親番の心得(土田のデジタル)
- 142.手役より組み合わせ優先 (約3分50秒)
- 143.ドラ(赤)1リーチが基本 (約3分20秒)
- 144.役牌ポンは速攻に限る (約3分30秒)
- 145.バラ手は大物仕掛け風味で (約4分20秒)
- 146.ダブ東でも鳴かない局を (約4分20秒)
- 147.シャンテン戻しはタブー (約4分)
- 148.先制リーチを躊躇しない (約4分)
- 149.形式テンパイを常に意識する (約5分10秒)
雀頭の作り方(土田のデジタル)
- 150.ノベタンを利用する (約3分50秒)
- 151.ペンチャンを利用する (約5分)
- 152.字牌を利用する (約4分40秒)
- 153.四連カンチャン形を利用する (約4分30秒)
- 154.亜リャンメンを利用する (約4分)
点棒が無いとき〔▲1万点下〕の心得(土田のデジタル)
- 155.ドラ(赤)プラスもう1役 (約3分30秒)
- 156.棒テン即リーは避ける (約5分)
- 157.良い待ち作りに専念する (約4分20秒)
- 158.親番ではスピード重視 (約3分40秒)
- 159.子方では安全牌を2枚持つ (約4分40秒)
- 160.子方では安手仕掛けは極力しない (約4分)
- 161.先制されたら向かわない (約4分20秒)
赤ドラ2枚持ちの進めかた(メンゼン手筋その1)(土田のデジタル)
- 162.赤周りの固めかた (約2分50秒)
- 163.残り2メンツの精度 (約4分40秒)
- 164.赤556・4赤55の活かしかた (約3分40秒)
- 165.カンチャン即リーチ (約3分)
- 166.くっつきテンパイ (約4分10秒)
赤ドラ2枚持ちの進めかた(メンゼン手筋その2)(土田のデジタル)
和了に近づける打ち方が基本ですから、打点に気持ちを奪われずに、形で勝負します。理想や夢を追う打点系の打ち方は極力避けます。
345の三色を狙うと![]()
![]() を落としますが、デジタル的には
を落としますが、デジタル的には![]() を外し、テンパイしやすく和了りやすい形を残します。
を外し、テンパイしやすく和了りやすい形を残します。
![]() を切れば、テンパイする牌は
を切れば、テンパイする牌は![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() です。筒子の重なり、もしくは索子が入れば
です。筒子の重なり、もしくは索子が入れば![]()
![]() で、萬子が入れば
で、萬子が入れば![]()
![]()
![]() でリーチが打てます。
でリーチが打てます。![]() を切れば、テンパイする牌は
を切れば、テンパイする牌は![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() で同じく6種類ありますので、この選択でも良いですが、
で同じく6種類ありますので、この選択でも良いですが、![]() が入ることを考慮すると
が入ることを考慮すると![]() を切るほうがいいです。
を切るほうがいいです。
打点系の打ち方では![]() を打ちます。
を打ちます。![]() が頭になっても、カン
が頭になっても、カン![]() ではリーチにいかないでしょうが、
ではリーチにいかないでしょうが、![]() を含めてもテンパイする牌は
を含めてもテンパイする牌は![]()
![]()
![]()
![]()
![]() の5種類で、1種類少なくなります。
の5種類で、1種類少なくなります。
さらに、カン![]() が残りやすい形ですから、和了に近づけるのかという疑問が残ります。運良く
が残りやすい形ですから、和了に近づけるのかという疑問が残ります。運良く![]() を引いて3、4、5の三色になったとしても苦しい待ちになります。運良く
を引いて3、4、5の三色になったとしても苦しい待ちになります。運良く![]() を引いて
を引いて![]()
![]()
![]() の待ちになっても、和了るのは概ね
の待ちになっても、和了るのは概ね![]() だと思います。
だと思います。
デジタルの思考でいくには、打点よりも形で勝負していきましょう。